若者が利用するSNSの一部では、「建設業界は若者離れして当たり前」「建設業界はオワコンだ」という声があります。
建設業界が若者離れをして当たり前と言われる理由には、若者が抱く業界への絶望感や、労働環境のキツさ、人間関係の悩みなどがあります。
この記事では、
などについて、SNSの声を元に詳しくお伝えしていきます。
ネットで見る建設業界の評判

インターネットでは、世間から見た建設業界の評判を知ることができます。
建設業界に対するネガティブな意見には、どのようなものがあるか確認していきましょう。
「建設業の若者離れは当たり前」という意見
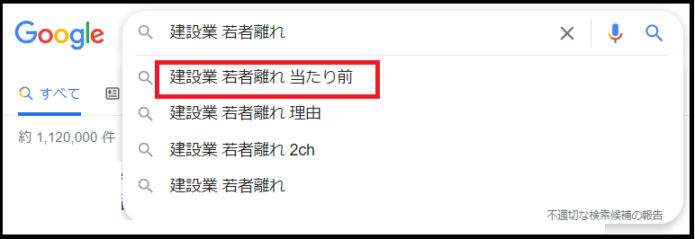
インターネットで「建設業の若者離れ」について調べると、多く見かけるのが「若者離れは当たり前」という意見。
建設業界は若者にとって、「時代に合った働き方ができていない業界」という印象を持たれているようです。
具体的な理由については、建設業が「若者離れは当たり前」「オワコン」と言われる4つの理由の項目でご紹介しています。
「建設業はオワコン」とも言われている
SNSでは、「若者離れは当たり前」という意見に加えて「建設業はオワコンだ」という意見もたくさん見つかりました。
オワコンとは「終わったコンテンツ」の略で、主に若年層がインターネットで利用する単語。
「建設業はオワコンだ」とは、時代に取り残された、働く魅力を感じない業界であるという意味合いです。
建設業が「若者離れは当たり前」「オワコン」と言われる4つの理由

建設業界が「若者離れして当たり前」「オワコンである」と思われる理由を調査した結果、大きく分けて4つの理由があることがわかりました。
SNS調査でわかった若者の本音を解説していきます。
①業界に対する絶望感が強い
残念ながら、建設業界に悪いイメージを持つ若者は多いです。
建設業界に対する絶望感は、建設業もしくは近い業界で実際に働いていた若者と、そうでない若者でイメージが異なります。以下で、それぞれのイメージを解説していきます。
建設業界(近い業界)で働いたことのある若者が抱くオワコン感
SNS調査で分かった、建設業界(近い業界)で働いたことのある若者が「オワコン」と思う理由には以下のようなものがありました。
・ゼネコンだけが儲かる業界構造が終わってる
・下請け仕事の搾取されている感、やりがいの持てなさがキツい
・仕事のできない先輩の尻ぬぐいをさせられて不公平さを感じる
・高齢者が多すぎる。頑張っても年功序列で不満
業界構造への不満
ゼネコン、サブコンや地場大手建設会社が最上位にいる構造を内部で目の当たりにすると、業界構造への不満が募ります。人によっては、「ゼネコンに入れなかった時点で負け組」「この業界は構造を変えられない、オワコンだ」という意識が生まれることもあります。
年功序列に対する不満
「高齢者」という多数派の属性への不満が募りやすいのも建設業界の特徴と言っていいでしょう。
業界的に高齢者の比率が高いことから、「仕事を頑張っても若いというだけで評価してもらえない」、「仕事のできない先輩の尻ぬぐいばかりしている」という不満が多く見られました。
若者が損をする構造を目の当たりにすると「若者離れして当たり前」という気持ちに繋がります。
業界経験者の不満は解消が難しい
業界構造への絶望感は、個人または会社単体でどうにかできる部分が少ないです。
上記のような理由で若者が建設業界を離れてしまっても、改善が難しいというのも困った点です。
建設業界で働いたことのない若者が抱くオワコン感
SNS調査で分かった、建設業界で働いたことのない若者が「オワコン」と思う理由には以下のようなものがありました。
・怒鳴られるのが当たり前とよく聞く。古い業界だと感じる
・早出と残業が当たり前という印象がある
・「見て覚えろ」と言って、仕事を教えてくれないらしい…
・事故で多くの人が死んでいるイメージがあり、危険そう
・肉体的にしんどそう。ホワイトカラーと比較した時に「負け組」感がある
3Kのイメージが払しょくできていない
建設業界で働いたことのない若者は、建設業のいわゆる3K(きつい・きたない・危険)」のイメージに対して絶望感を持っています。
労働環境の悪い建設会社がいまだ残っているのは事実ですが、多くの建設会社では時代に沿った職場環境の改善が進んでいます。
しかし、一部の建設会社で起きた、悪い意味でインパクトのあるニュースはインターネットで瞬時に広まります。それが業界全体のことのようにとらえられてしまうと、上記のような印象だけが残ります。
会社の労働環境を改善し、外部に根気よく発信していくことでイメージを払しょくしていく必要があります。
②実際に働いて労働環境が悪かった
実際に建設業で働いた若者のうち、労働環境の悪い会社に当たってしまった人は、働いていた会社の悪い部分を建設業全体のイメージととらえ、建設業界から他業界に離れてしまいます。
一度離れた若者をもう一度建設業界に呼び戻すことはほぼ不可能でしょう。
③建設業界の人間と気が合わない
SNSで見られる不満の中で多くあったのが「会社の先輩と話が合わない」というキーワードでした。
例えば「興味のないギャンブルや男女関係の話がキツい」「釣りやキャンプに興味がないのに自分以外みんなやっていて気まずい」というような声が上がっています。
若手の孤立を避けることが大切
建設業界に限った話ではありませんが、先輩と話が合わないと楽しくなく、結果として職場で孤立してしまい若者離れが起こることがあります。特に高齢者が多い建設業界では、若手とベテラン間での話題が合わずに孤立してしまうことが多く起こっているのではないでしょうか。
こういった時、年長者が若手に寄り添うことはもちろん大切なのですが、最も有効な手段は複数人の同世代を同時期に採用して、若者が孤立するのを避けることです。
とはいえ、ただでさえ採用が厳しい時代に複数名を入社させることは至難の業です。面接時に人柄を把握しておき、教育係として性格の合いそうな先輩をつけるなど孤立させない対策をとることで、会社に馴染んでもらうような配慮が必要です。
④ピーク時のキツさが目立つ
仕事量に変動があり、悪い部分が目立っている
建設業界は繁忙期や工期末になると忙しく、会社によっては暇な時期と忙しい時期の仕事量が大きく変動します。特に現場監督など、現場の工程を管理するポジションは、ピーク時になると「日付をまたいでも帰れない」というようなキツい体験をしていることもあります。
死亡事故など、悪いニュースが印象に残ってしまう
現場での死亡事故が起こるとニュースに取り上げられるため、「建設業の仕事はよく人が死んでいる」というイメージも抱かれやすいです。
このようなエピソードは非常にインパクトがあり、若者の建設業のイメージにも結び付きやすいため、建設業に入る前にすでに若者が離れてしまうことも多いのです。
しかし、これらのエピソードはすべての建設会社に該当するわけではありません。残業時間や死亡事故の発生率を公表するなど、自社の実情を根気強く発信していくことで、会社単位でのイメージの払しょくは可能です。
若者に建設業界内の常識は通用しない

若者の心理を理解する上で重要なのは、若者に「うちの会社では当たり前」「建設業界では当たり前」は通じないという前提で考えるべきだということです。
その理由のひとつは、インターネットの普及です。今の時代、インターネットやSNSで簡単に建設業界以外の世界を知ることができます。
SNSの投稿で待遇のいい友人の職場を知ったり、愚痴を書いたら「ブラックだ」とコメントがついたりと、他の業界で働く人の価値観に触れる機会が多い現代の若者。待遇が悪い部分があればすぐに自分は職場環境に恵まれていない、建設業界からは離れるべきかもしれないと感じてしまうのです。
建設業界にできる若者離れ対策は?

「建設業はオワコン」「若者離れが当たり前」と言われる現状を変えるためにはどうしたらいいのでしょうか。
他業界と比べた建設業の優位性をアピールする
若者離れを解消するカギとなるのは、他業界と比べた建設業の優位性を提示することです。
若者を自社に引き込みたいのであれば、建設業界内だけのものさしで待遇の良し悪しを図るのではなく、ほかの業界と比較しても魅力的に感じる会社作りをする必要があります。
また、若者に建設業の良さを伝える際は、根拠となるデータや数字を提示することも大切です。事実を提示しつつ建設業の魅力を伝えることができれば、若者を引き込むことは可能です。
建設業が他業界に比べて優れている例を、以下で解説していきます。
建設業の賃金の高さをアピールする
建設業は肉体的に厳しい部分がある分、賃金やボーナスは他業界よりも高い傾向があります。これは、厚生労働省や東京都の調査ではっきりと裏付けが取れている事実です。
大多数の労働者にとって、賃金の高さは仕事を決める重要な指標です。「建設業は稼げる仕事である」ということをアピールしていくことは若者離れ対策として有効です。
◆ 建設業の平均年収は567万!年齢別・業種別・地域別など詳細データも紹介の記事では、建設業界の年収を年齢別・業種別・地域別など細かくご紹介しています!
◆ 【2024年夏最新】建設業の賞与(ボーナス)速報|中小企業は54万円の記事では、建設業のボーナス事情を会社規模別にご紹介しています!
建設業の安定性をアピールする
建設業界は職人の高齢化率が非常に高く人材不足の背景があるため、若いうちから技術を身に着ければ将来仕事に困ることがない、非常に安定性の高い業界です。
建設業で身につく技術は生涯役立つということを、若者に伝えていくことが大切です。
個人事業主や起業の道をアピールする
建設業界で働き技術を身につけると、独立するという道が生まれます。
個人事業主として独立すれば、自分で頑張った分だけ稼ぐことができます。このことは、若者にとっても魅力に映るポイントです。
まとめ~建設業はオワコン・若者離れが当たり前と言われないために~
建設業界全体についてしまっている悪いイメージを払しょくすることは簡単ではありません。
まずは「自社は旧来の建設会社とは違う」と言えるよう、自分の周りの労働環境改善に取り組み、それを地道に発信することが大切です。
旧来のイメージを脱却できない建設業者に若者が集まることはありません。変わらなければ会社は存続不可能であることを意識し、改善していきましょう。
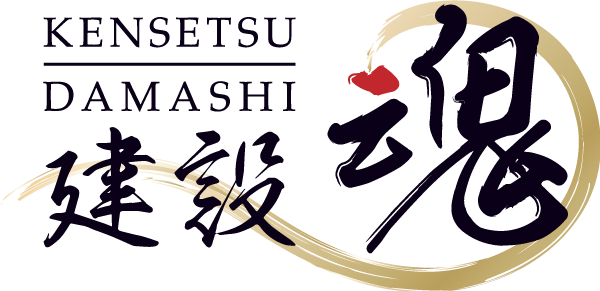



コメント
たまたま見かけて読ませて頂きましたが、最後の平均年収の所。
当方は九州の方なのですが、その半分程度なので、ちょっと記事の信憑性が薄れてしまいました。
ゼネコンだけが儲かり、下請け潰し状態なのは実感しています。
コメントありがとうございます。
記事中の平均年収については、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」に基づいた全国平均の数値を参考にしております。
とはいえ、現場の実情についてのご指摘ももっともで、実際の声として非常に貴重だと感じております。
今後の記事制作にも活かしてまいります。ご意見ありがとうございました。