自社でパワハラが発生したら?
自社でパワハラが発生したとき、どのように対応すればいいか考えたことはあるでしょうか。
パワハラの相談件数は年々増加しています。万が一の時に備えて、対応策を今から考えておきましょう。
本記事では、パワハラが発生した場合の初期対応~解決に向けた動きを解説していきます。
パワハラの定義と発生させない方法が知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!
パワハラ発生~解決までの流れ

現場からパワハラの相談が上がってきたと想定して、解決までにどのような道筋で進んでいくのかを解説していきます。
パワハラ相談窓口を設定し、相談を受け付ける
「現場で上司に殴られた」「日常的に同僚から暴言を受けている」など、パワハラに関する相談が上がってきた場合、まずは一時窓口の担当者が相談者への面談を実施します。できるだけ最初の段階で解決できることが理想ですので、気軽に相談できる窓口をあらかじめ決めておくことが早期解決に繋がります。窓口担当者の例は、以下の通りです。
人事担当:会社に人事担当がいる場合は、人事担当者が窓口を兼任することが多いです
代表:小規模の企業で人事担当がない場合は、代表自ら対応しましょう
職長・現場監理者:職人間の問題の場合は、現場を統括している人が窓口となることもできます。しかし、同じ現場にいるからこそ分かることもありますが、かえって話しにくい場合もあるかもしれませんので、できれば現場を離れた第三者が面談を実施することが望ましいです
相談窓口を決めたら、社員全員に担当者の名前、電話番号、メールアドレスを伝達し、いつでも相談を受け付けられるようにしましょう。
ちなみに、内部の相談窓口だけでなく外部の相談窓口を設けている企業もあります。具体的には弁護士や社労士の事務所、ハラスメント対策を行っているコンサルティング会社などを外部相談窓口として置いている場合が多いです。人員の余裕がない場合や内部に適任がいない場合、外部に窓口を置くという方法もあります。
面談を実施する
担当者がパワハラ被害の相談者に面談を実施します。面談は、相談者の悩みや不安に感じていること聞きとることが目的です。面談の時点で解説しようとはせず、まずは聞くことに専念しましょう。
面談時には、気を付けるべき5つのポイントがあります。
① 秘密は厳守する。また、面談の前には相談者に「面談の内容は誰にも知らされず、評価にも影響しない」ということを伝え、安心して相談ができるようにする
② 面談場所は、相談の声が聞こえたり他の社員に気づかれない場所を設定する(会社だと難しい場合は喫茶店などでも可)
③ 相談者の話はゆっくり聴き、話をせかしたり、途中で否定しない
④ 1回の相談時間は50分程度とし、時間内に終わらない場合は、次の相談日を設定して切り上げる ※ 相談者が気持ちを切り替える時間や冷静な時間をもつことになり、相談の効果を高めます
⑤ 「くだらない」「大した問題ではない」と軽くとらえずに、相談者の気持ちに寄りそい真剣に話を聞く
事実関係を確認する
面談の後は相談者の同意をとった上、事実確認を実施します。
まずは、行為者(パワハラを行っているとされる人)に対して事実確認を行います。相談者と行為者の言い分が一致しない場合は、現場を知る第三者への聞き取りを実施します。
※ 相談者が面談のみを希望した場合は、この工程を含め以降の工程は全て実施しません。了解を得ずに事実確認を進めてしまうとトラブルが悪化する原因になります。
事実確認時は、以下3つのポイントに気を付けて行ってください。
① 相談者、行為者のどちらにも肩入れせず中立的な立場で行為者の話を聴きましょう。まだパワハラがあったことが確定したわけではないので、この時点で行為者に問題があると決めつけてはいけません
② 行為者には、相談者の認識に誤解があった場合でも報復などは厳禁であることを伝えましょう。
③ 第三者に話を聞く際、守秘義務について十分理解してもらい話が外に漏れないようにしましょう。必要な人を絞り、事実確認を行う人数は最小限にするのがいいでしょう
パワハラにあたるか・あたらないかを判断する
聞き取りが完了したら、行為者のふるまいがパワハラにあたるか・あたらないかの判断を行います。
パワハラに当たるかどうかの判断軸は、下記のとおりです。
① 行為者の行いは、パワハラの6つの定義*のどれかに該当しているか
② 行為者のふるまいについて、行動・目的・動機は業務上の指導として適切とは言えないものであったか
③ 行為者のふるまいは、悪質で、慢性的に繰り返されていたのか
*6つの定義についてはこちらの記事をご参照ください。上記3つの項目の全てが該当していて、かつ行為者もその振る舞いについて認めている場合、パワハラがあったとみなします。
事実確認の内容が相談者・行為者・第三者で食い違っている場合は、判断の際に注意が必要です。情報を中立的に判断するようにしてください。事実確認が取れないうちに判断を急がず、再度面談や事実確認に立ち帰って情報を精査することも場合によっては必要となります。
処分方法・和解策を考える
パワハラがあったと認められた場合は、その後の解決策について考えます。
相談者が行為者の処分を望んでいる場合は処分を検討し、就業規則等に罰則が設けられている場合、規則に沿って処分を行います。
処分の種類としては、下記のようなものが挙げられます。
処分の種類:減給、降格、けん責(始末書の提出など) 、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇
なお、解雇など重い処分を検討している場合は、会社のみで判断せず弁護士や社労士に相談の上判断を進めるといいでしょう。
当事者同士が納得できるのであれば、処分よりも和解を選択しておきたいところです。相談者が一度は処分を望んだ場合でも、和解の余地がありそうかを確認し、平和的解決の道を探して下さい。
相談者への提案としては、以下のような例が挙げられます。
相手がパワハラを認めて反省している。一度だけ話しあいをする余地はないか
行為者が今後態度を改めるとすれば、もう一度一緒に働いていけそうか
※ 相談者へ和解を強要することはせず、必ず提案という形をとって下さい。
行為者・相談者へのフォローを行う
処分・和解など行為者への対応が決定した後は、フォローも重要となります。
相談者・行為者の両方に、事実関係についての調査結果や、対応の内容、会社としての考え方を説明し、理解を得るようにしましょう。
また同じ問題が起きないよう、継続的にフォローを行ってください。
特に、相談者にも問題があったと認められ、行為者に対して処分なしと判断した場合は、相談者に納得してもらうため丁寧な説明が必要です。
仕事の行い方や、行動にどのような問題があったのかを伝え、それに対して行為者がどのような目的で指導を行っていたのかを細やかに説明し、今後の人間関係が円滑に進むように細心の注意を払う必要があります。
パワハラ対応策についてのまとめ
パワハラ問題は、相談者、行為者そして第三者の意見を冷静に聞き、事実を把握することがなにより重要です。
誤った判断は、社員の人生を取り返しのつかないことにしてしまいます。決断を急がず、正確な事実確認を進めるため、弁護士・社労士などの意見も参考にしながら問題について取り組むことをお勧めします。
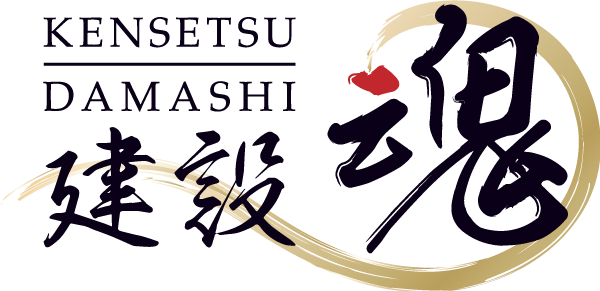


コメント
グーグル検索で見つけました。
保全、電工、産業機械の電気担当。必ずパワハラがセットでした。
ちょっとやそっとじゃあぶれないよう働いてましたが、直近の会社中国人部長「死んでくれ」長物でおどしてきた。→条件付きで5月退職。
パワハラ防止宣言する会社なんてあるんですかね?あったら履歴書もっていきたいくらいです。